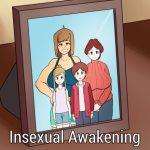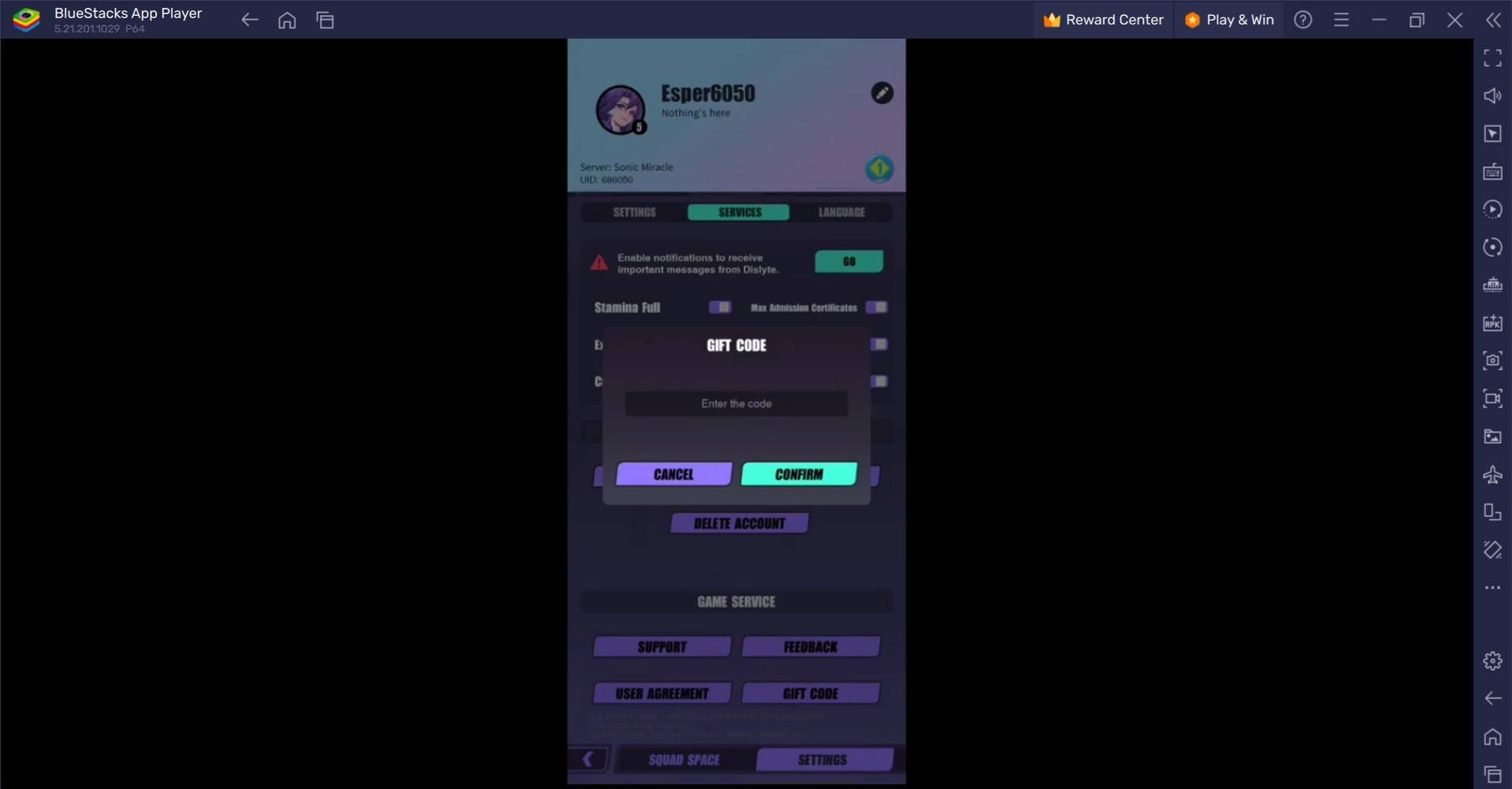アサシンクリードシリーズで最も忘れられない瞬間の一つは、『アサシンクリード3』の序盤、ヘイサム・ケンウェイが新世界でチームを結成するシーンです。当初はアサシンとして登場したヘイサムのカリスマ的な統率力と隠し刃は、特にネイティブアメリカンの解放やイギリス兵との対峙といった英雄的行為の後に、この推測を裏付けるかのように思えました。しかし、彼がテンプル騎士団の信条「理解の父が我らを導かんことを」と唱えた瞬間、衝撃的な真実が明らかにされます。プレイヤーは突然、宿敵のために任務を遂行していたことに気付くのです。

この見事なストーリーテリングは、アサシンクリードシリーズの頂点を示しています。初代作品はターゲット暗殺を軸にした魅力的なゲームメカニクスを確立しましたが、キャラクターの深みに欠けていました。『アサシンクリード2』ではカリスマ的な主人公エツィオ・アウディトーレによって改善されたものの、悪役の描写は不十分なままでした。『アサシンクリード3』において初めて、主人公コナーとヘイサムなどの敵キャラクターが同等に掘り下げられ、比類ない物語の一貫性とキャラクター深度が実現されたのです。
拡大の代償
近年のRPG時代は商業的成功を収めていますが、シリーズが本来の道を見失ったという意見が大勢を占めています。神話的なボス戦や『シャドウズ』の安易な代弁など、その主因については議論が続いています。しかし、根本的な問題はより深いところにあると私は考えます——広大なオープンワールドの陰で、キャラクター主導のストーリーテリングが徐々に蝕まれていることです。
シリーズがRPGライト化する中で導入されたダイアログツリー、XPシステム、マイクロトランザクションは、皮肉にもマップが拡大するほど物語を薄めました。『オリジンズ』のバエクのような現代の主人公たちは、AC3のコナーのような明確な特徴を持つキャラクターと比べ、プレイヤー選択による個性の希薄化に悩まされています。
「かつての作品がモラルの曖昧さを糧にしていたのに対し、現在の作品は単純なアサシン対テンプルの二項対立に陥っている」
Xbox 360/PS3時代はゲーム史上最高の脚本を生み出しました:
- エツィオのフィレンツェでの熱弁(「我に続くな!」)
- ヘイサムがコナーに遺した悲劇的な最期の言葉
- 哲学的で深みのあるテンプル騎士の最期の独白

失われたモラルの曖昧さの技術
シリーズ最大の物語的強みは、グレーゾーンの道徳観を探求することにありました:
- テンプル騎士ウィリアム・ジョンソンがネイティブアメリカンの虐殺を防げると主張する場面
- トーマス・ヒッキーがコナーの聖戦の空虚さを暴く場面
- ワシントンに関わるコナーの村への壊滅的な裏切り
この哲学的な豊かさは近年の作品では薄れています。「エツィオズ・ファミリー」のような記憶に残る瞬間は、歴史的スペクタクルではなくキャラクターの感情を結晶化させたからこそ共感を呼んだのです。現代のタイトルが壮大なスケールを誇る一方で、シリーズの黄金時代を定義した痛切な個人的焦点が物語から失われています。
シリーズは存亡の危機に直面しています:広大なオープンワールドと親密なストーリーテリングは共存できるのか? 技術の進歩が息を呑むような歴史再現を可能にする一方で、キャラクターの深みという代償を払っています。終わりなきコンテンツを物語の精度より優先する業界において、アサシンクリードの最も豊かな物語は過去のものになりつつあるのかもしれません。
 家
家  ナビゲーション
ナビゲーション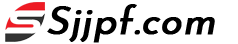






 最新記事
最新記事

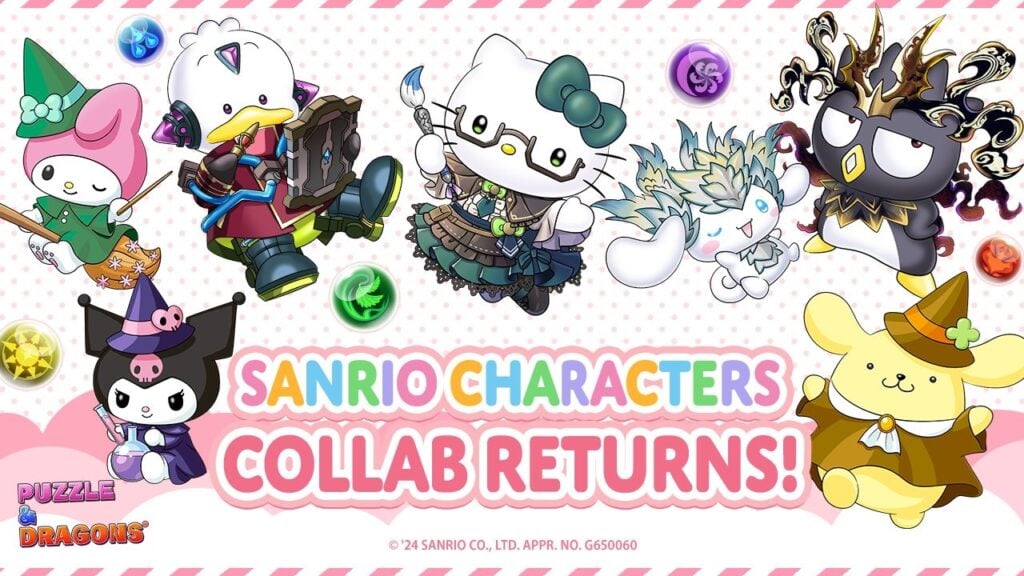








 最新のゲーム
最新のゲーム